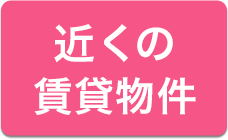「七里ケ浜」から直線距離で半径3km以内の観光スポット・旅行・レジャーを探す/距離が近い順 (1~49施設)
①施設までの距離は直線距離となります。目安としてご活用ください。
②また ボタンをクリックすると七里ケ浜から目的施設までの徒歩経路を検索できます。
ボタンをクリックすると七里ケ浜から目的施設までの徒歩経路を検索できます。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 龍口明神社は古墳時代の538年創建で、鎌倉市に現存する一番古い神社と言われています。五頭龍大神と玉依姫命を祀っています。五頭龍大神は国家安泰・心願成就・交通安全・縁結び、玉依姫命は縁結び・子授け・安産の神として信仰されています。 玉依姫命は神武天皇の母、海神族の祖先で、龍神として崇められたと伝えられています。五頭龍大神とは、鎌倉と江ノ島に伝わる五頭龍と弁財天の伝説に登場する一身五頭の龍神で、江の島の弁財天に悪業を戒められた龍であり、龍が改心し岩山と化した後、津村(腰越および隣接の現鎌倉市津一帯)の村人達が、龍の口にあたる岩上(龍口)に社を築いて、村の鎮守としたことが、龍口明神社の発祥と伝えられています。と言うことで、現在の西鎌倉では無く、当初は龍口寺西隣にありました。大正12年(1923年)、関東大震災により全壊し、その後、昭和8年(1933年)に改築しました。しかし、鎌倉時代に刑場として使用された時期もあったこの地の祟りを恐れた氏子の要望により、 昭和53年(1978年)に江の島を遠望し、龍の胴にあたる現在の地へと移転したそうです。 最寄り駅は湘南モノレール線西鎌倉駅で、歩いて5分と案内されていますが、坂道ということもあり、もう少しかかるかもしれません。閑静な住宅地の中にあり、境御神木のタブノキや五頭龍大神の銅像などがパワースポットとして人気になっています。 また、移転前の龍口(龍口寺)には、鎌倉市津1番地が飛び地として残っています。龍口明神社跡は中に入れないようになっていますが、通りから鳥居が見えます。 日本三大弁財天として名高い江島神社とは夫婦神社(江島神社が女、龍口明神社が男)とされ、江島神社と龍口明神社は併せてお参りされるがおすすめであると言われています。また、現存する一番古い神社という事ですので、移転前の龍口明神社跡にも立ち寄りたいですね。この辺りは歴史のある神社も多く、神社仏閣巡りに良いところです。併せてお参りに行ってみてください。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 成就院は、弘法大師が修行された護摩壇跡に第3代執権の北条泰時が京都から辰斎上人を招いて、1219年建立しました。 鎌倉エリアでアジサイ寺として有名でしたが、2019年の創建800年に向けての参道工事にて一面のアジナイではなくなっています。 以前参道には「般若心経」の文字数と同じ262株のアジサイがありましたが、30株ぐらいまでに減ったそうです。 参道のアジサイは東北へのご縁が広がることを願って、宮城県 南三陸町へ送り、現在はアジサイの代わりに宮城県県花のハギを植えているそうです。 一面のアジサイはもう見られませんが、今後はハギを楽しみにしたいです。 山門前から見える弧を描いて広がる由比ヶ浜、材木座海岸の一望は健在で、鎌倉でも屈指の絶景ポイントになっています。 コロナ禍でお守りやご朱印などセルフ対応でした。 前回はコロナなど知らない頃の暑い日の参拝だったため、暑さに気をつけての心づかいと塩味せんべいをくださったこと、懐かしく思いました。 平穏な日々に戻ることを祈るばかりです。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 江ノ島電鉄の極楽寺駅と鎌倉の大仏様で有名な高徳院がある長谷駅の間に神社があります。長谷駅から長谷寺に向かって歩いて途中を住宅街の中に入ります。ひたすら住宅街を歩いていくと神社の裏手の鳥居が見えて来ます。他には、長谷駅から極楽寺駅に戻る感じて線路に近い道をいくと正面の鳥居が見えて来ます。江ノ島電鉄の線路の側にあるので電車の中からも、神社が見えます。 読み方は「ごりょうじんじや」と読みます。私は「みたま」と読むと思ってました笑笑。そして、「権五郎神社」とも呼ばれるそうで、鎌倉七福神のひとつに数えられています。そういえば、七福神のお参りする社がありました笑笑。通りすがって参拝せず帰って来てしまいましたが、皆さんは是非お参りしてください。 梅雨時は、紫陽花が咲いていてとても風情があります。本殿の社の隣には海を守る神様が祀られていて、鎌倉に住む人たちの守り神として地域に密着していたんだなと思いました。鳥居から中に入ると、住宅街の中にあり観光客で賑わう通りから外れているせいか、雨が降っていれば、静かで雨音しか聞こえてこない感じです。そしてなぜか、空気が冷たく感じます。物足りないと感じるかもしれませんが、1人でぼーっとしたい人はおすすめです。曇っている時にお出かけの際は、羽織るものを持って行った方がいいです。 因みに、御朱印はちゃんと手書きで書いてくれます。猫のスタンプが押してあるのが可愛くてとてもお気に入りです。 もしかしたら天気のいい日には、猫ちゃんに会えるのかもしれません。 今度お参りに行った時は、猫ちゃんのスタンプの理由を聞いてみようと思います。 わかる人は是非ホームメイトリサーチに投稿して下さい。 私も次に行った時は猫ちゃんがいるか見に行きたいと思います。 おみくじも昔ながらの普通のおみくじで、200円でくじを引く事ができます。普通のくじと、恋みくじの2種類あるので、デートの時は恋みくじを引くのもいいと思います。 そして、お参りする時は早めに行かないと御朱印をもらう事ができなくなるかもしれませんので、インターネットで確認して下さい。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 神奈川県鎌倉市長谷にある収玄寺は、江ノ電長谷駅から徒歩わずか1分の場所に位置する日蓮宗の寺院です。観光客で賑わう長谷寺や鎌倉大仏への道中にありながら、静かで落ち着いた雰囲気を保っています。境内は四季折々の花々が彩り、特に春の桜や夏のアジサイ、秋のシュウメイギクなどが訪れる人々の目を楽しませています 。 ? ? この寺院は、鎌倉時代の武士で日蓮の信徒であった四条金吾頼基の邸宅跡に建てられました。境内には「四条金吾邸址」と刻まれた大きな石碑があり、その文字は日露戦争で連合艦隊を率いた東郷平八郎によるものです 。また、境内にはカフェ「蕪珈琲」も併設されており、参拝後のひとときを過ごすのに最適です 。 ? ? 境内はは、綺麗に手入れされていて、赤や白、ピンクに青、色とりどりのアジサイが美しく、静かに歴史を感じられる場所としても評価されています。 ? ? 収玄寺は、華やかな観光地の喧騒から少し離れ、鎌倉の歴史と自然を静かに感じられる場所です。長谷エリアを訪れる際には、ぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 鎌倉市手広にあるお寺です。 手広の交差点を腰越方面に7〜8分ほど歩いたところにあります。私はお散歩がてら家から歩いて行ったのですが、最寄り駅の大船や藤沢から歩くには少々遠いのでバスを利用した方が良いと思います。 入口の前は駐車スペースなのか少々広くなっていて数台であれば駐車することが出来そうでした。 山門の両脇にある石碑や看板に「鎖大師」や「鎖弘法大師」と書いてあったので少々不思議に思いました。看板によると本尊の鎖大師像は重要文化財に指定されているようです。 緑色の屋根の山門をくぐるとまっすぐな参道になっており、その両側に建物と石像がある造りとなっていました。 入って直ぐの右側に手の込んだ立派な屋根の鐘楼があり、感動しました。 更に参道を進んで行くと本堂が右側にあり、お線香が売っていたので購入してお参りをしました。 扁額に「鎖大師」と書いてあったので、この中にあるのかと思いましたが扉が閉まっていたので見ることが出来ず残念でした。 参道を挟んで本堂の向かい側に五輪塔童子という小さな石像がありました。5体の石像があり、それぞれがラッキーカラーと健康運や勝負運等のご利益を持っているようです。このような石像を見たことは無かったので、良い体験をすることが出来ました。 「鎖大師」というのが気になったので帰宅後に調べてみると、弘法大師木像の膝が鎖で繋がっていて動くようになっていることから「鎖大師」と呼ばれるようになったそうです。 弘法大師自身が作ったと伝えられているようです。 年に5回開帳されるとのことなので、機会があれば行ってみたいと思います。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 鎌倉を訪れた際に、長年一度は見てみたいと思っていた鎌倉大仏(高徳院)を訪れました。写真では何度も見たことがありましたが、実際に目の前に立ってみると、その大きさと存在感に圧倒されます。高さ約11メートル、重さ約121トンとされるこの青銅製の阿弥陀如来像は、想像以上の迫力で、静かに佇むその姿からはどこか温かさと厳かさが同時に伝わってきました。 大仏は屋外に設置されており、青空や季節の風景と調和してとても美しいです。私が訪れた日は晴天で、青空を背景にした大仏の姿はとても写真映えし、観光客も多くカメラを構えていました。外国人観光客も多く、世界中からこの地を訪れていることが感じられました。特に欧米やアジアからの旅行者が多く、世界的な観光地としての魅力を改めて実感しました。 参拝料は大人300円と良心的で、さらに追加料金(20円)で大仏の胎内(内部)に入ることもできます。内部は狭いですが、鋳造の構造や補強の跡などが見学できて、とても興味深い体験でした。外からは想像もつかない、内部構造の工夫や歴史を感じることができ、より一層この大仏への敬意が深まりました。 高徳院の敷地自体はそれほど広くはないものの、静かで落ち着いた雰囲気があり、自然に囲まれた環境も魅力的です。大仏の背後には緑の木々が広がり、春は桜、秋は紅葉と、季節ごとに違った表情が楽しめるそうです。また、大仏の前にはベンチがあり、ゆっくり腰掛けて眺めることもできます。時間を忘れてしばらく佇んでいたくなる、そんな穏やかな空間でした。 アクセスについても、鎌倉駅から江ノ電に乗って長谷駅で下車し、そこから徒歩約10分ほどと便利です。駅からの道のりも観光地らしく、土産物屋やカフェが立ち並び、散策するのが楽しいエリアです。途中で食べた鎌倉名物のしらす丼や、和菓子店で購入した抹茶羊羹も旅の良い思い出になりました。 さらに、大仏見学の後には近くの長谷寺や由比ヶ浜にも足を延ばすことができ、1日で鎌倉の魅力をぎゅっと楽しめます。歴史好きの方はもちろん、カップルや家族連れにもおすすめのスポットです。 鎌倉大仏はただ大きいだけでなく、その穏やかな表情、歴史的背景、そして人々に寄り添うような空気感がとても印象的でした。ぜひ一度、自分の目でこの大仏の優しさと迫力を体感してみてください。期待を裏切らない、心に残る観光体験になるはずです。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 鎌倉を訪れた際に、長年一度は見てみたいと思っていた鎌倉大仏(高徳院)を訪れました。写真では何度も見たことがありましたが、実際に目の前に立ってみると、その大きさと存在感に圧倒されます。高さ約11メートル、重さ約121トンとされるこの青銅製の阿弥陀如来像は、想像以上の迫力で、静かに佇むその姿からはどこか温かさと厳かさが同時に伝わってきました。 大仏は屋外に設置されており、青空や季節の風景と調和してとても美しいです。私が訪れた日は晴天で、青空を背景にした大仏の姿はとても写真映えし、観光客も多くカメラを構えていました。外国人観光客も多く、世界中からこの地を訪れていることが感じられました。特に欧米やアジアからの旅行者が多く、世界的な観光地としての魅力を改めて実感しました。 参拝料は大人300円と良心的で、さらに追加料金(20円)で大仏の胎内(内部)に入ることもできます。内部は狭いですが、鋳造の構造や補強の跡などが見学できて、とても興味深い体験でした。外からは想像もつかない、内部構造の工夫や歴史を感じることができ、より一層この大仏への敬意が深まりました。 高徳院の敷地自体はそれほど広くはないものの、静かで落ち着いた雰囲気があり、自然に囲まれた環境も魅力的です。大仏の背後には緑の木々が広がり、春は桜、秋は紅葉と、季節ごとに違った表情が楽しめるそうです。また、大仏の前にはベンチがあり、ゆっくり腰掛けて眺めることもできます。時間を忘れてしばらく佇んでいたくなる、そんな穏やかな空間でした。 アクセスについても、鎌倉駅から江ノ電に乗って長谷駅で下車し、そこから徒歩約10分ほどと便利です。駅からの道のりも観光地らしく、土産物屋やカフェが立ち並び、散策するのが楽しいエリアです。途中で食べた鎌倉名物のしらす丼や、和菓子店で購入した抹茶羊羹も旅の良い思い出になりました。 さらに、大仏見学の後には近くの長谷寺や由比ヶ浜にも足を延ばすことができ、1日で鎌倉の魅力をぎゅっと楽しめます。歴史好きの方はもちろん、カップルや家族連れにもおすすめのスポットです。 鎌倉大仏はただ大きいだけでなく、その穏やかな表情、歴史的背景、そして人々に寄り添うような空気感がとても印象的でした。ぜひ一度、自分の目でこの大仏の優しさと迫力を体感してみてください。期待を裏切らない、心に残る観光体験になるはずです。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 江ノ電の江の島駅から徒歩3分のところにある龍口寺。神奈川県藤沢市片瀬の龍口刑場跡に建つ日蓮宗の本山、かつて刑場があった場所で、鎌倉幕府の反感を買った日蓮聖人が捕らえられて連行されたところだそうです。 境内には、欅作りの大本堂、神奈川県唯一の木造五重塔、日蓮聖人が入れられたという御霊窟は、日蓮聖人の銅像が安置されている。他にも鐘楼堂、仏舎利塔、七面堂、妙見堂など、かなり広かったです。 鎌倉に用事があって出かけたのですが、前日にみたネット記事で、寅の日に毘沙門天さんを祀る神社仏閣にお参りすると良いとあったので、まさに寅の日、お参りしてきました。 両脇に黄色に染まった銀杏がある仁王門には、口乃龍と額がかかっていて、天井には龍がいました。龍ノ口刑場跡、山門、龍口明神社などがある境内を進むと、正面には立派な本堂がありました。本堂に入り、ご本尊にお参りして、脇にある授与所でご朱印をいただきました。 本堂の前には、格子のついた横穴があり、むかし日蓮聖人が入れられた土牢との説明がありました。 本堂の裏には、仏舎利塔や経八稲荷堂、五重塔があるそうですが、時間が無かったため、今回は回れなかったので、またゆっくり参拝したいと思います。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- こんにちは。 本日は江ノ島大橋と江ノ島周辺のおすすめスポットに付いてご紹介致しますね。 まず、江ノ島大橋とは江の島と本土とを結ぶ橋で、厳密には西側の「江の島弁天橋」と東側の「江の島大橋」に分かれている様です。一般には両橋を含めて江の島大橋、江ノ島大橋と呼びます。江ノ島大橋を渡った事がある方は知っていると思いますが、富士山がとても綺麗に見えます。 続きまして、江ノ島周辺のおすすめスポットをご紹介致します。 まずはなんと言っても、江ノ島についてですね。 島全体がパワースポットであるといえる江ノ島。女神三姉妹が祀られている江島神社がメインの観光スポットです。詳しくお伝えしますと、島内にある辺津宮(へつみや)、中津宮(なかつみや)、奥津宮(おくつみや)の三社を総称して江島神社という様です。海の守護神である女神が祀られていて、金運や恋愛運、勝負運、芸能運を高めるパワースポットとして有名な神社となっております。また、江ノ島シーキャンドル(展望灯台)もとても眺めが良く、夜にはイルミネーションもあり、こちらも人気スポットですね。また、東京オリンピックでもセーリングの競技会場になった日本最大級の公共ヨットハーバー。江ノ島沖では一年を通して数多くのレースが行われ、江ノ島ヨットハーバーから出航するヨットマンたちで賑わっております。江ノ島から見下ろす江の島ヨットハーバーもとても絵になる絶景ですよ。 続きまして、御家族、お子様にも人気な新江ノ島水族館です。相模湾に面し、東に江ノ島、西に富士山を見渡せる好立地にあり、江ノ島の観光では絶対にはずせない水族館。相模湾に生息する生き物をテーマにした展示やダイビングショーは、子供から大人まで多くの人を魅了してやまない水族館となっております。 食事に関しても、海の幸を使った料理が楽しめ、海産物を中心とした種類豊富な品揃えのお土産が沢山あります。 この他にも、まだまだ紹介しきれない人気スポットや観光地も沢山あり、必ず充実した1日になる事は間違いないので、行った事の無い方は是非1度行って見て下さい。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 江ノ島電鉄の極楽寺駅と鎌倉の大仏様で有名な高徳院がある長谷駅の間に神社があります。長谷駅から長谷寺に向かって歩いて途中を住宅街の中に入ります。ひたすら住宅街を歩いていくと神社の裏手の鳥居が見えて来ます。他には、長谷駅から極楽寺駅に戻る感じて線路に近い道をいくと正面の鳥居が見えて来ます。江ノ島電鉄の線路の側にあるので電車の中からも、神社が見えます。 読み方は「ごりょうじんじや」と読みます。私は「みたま」と読むと思ってました笑笑。そして、「権五郎神社」とも呼ばれるそうで、鎌倉七福神のひとつに数えられています。そういえば、七福神のお参りする社がありました笑笑。通りすがって参拝せず帰って来てしまいましたが、皆さんは是非お参りしてください。 梅雨時は、紫陽花が咲いていてとても風情があります。本殿の社の隣には海を守る神様が祀られていて、鎌倉に住む人たちの守り神として地域に密着していたんだなと思いました。鳥居から中に入ると、住宅街の中にあり観光客で賑わう通りから外れているせいか、雨が降っていれば、静かで雨音しか聞こえてこない感じです。そしてなぜか、空気が冷たく感じます。物足りないと感じるかもしれませんが、1人でぼーっとしたい人はおすすめです。曇っている時にお出かけの際は、羽織るものを持って行った方がいいです。 因みに、御朱印はちゃんと手書きで書いてくれます。猫のスタンプが押してあるのが可愛くてとてもお気に入りです。 もしかしたら天気のいい日には、猫ちゃんに会えるのかもしれません。 今度お参りに行った時は、猫ちゃんのスタンプの理由を聞いてみようと思います。 わかる人は是非ホームメイトリサーチに投稿して下さい。 私も次に行った時は猫ちゃんがいるか見に行きたいと思います。 おみくじも昔ながらの普通のおみくじで、200円でくじを引く事ができます。普通のくじと、恋みくじの2種類あるので、デートの時は恋みくじを引くのもいいと思います。 そして、お参りする時は早めに行かないと御朱印をもらう事ができなくなるかもしれませんので、インターネットで確認して下さい。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 成就院は、弘法大師が修行された護摩壇跡に第3代執権の北条泰時が京都から辰斎上人を招いて、1219年建立しました。 鎌倉エリアでアジサイ寺として有名でしたが、2019年の創建800年に向けての参道工事にて一面のアジナイではなくなっています。 以前参道には「般若心経」の文字数と同じ262株のアジサイがありましたが、30株ぐらいまでに減ったそうです。 参道のアジサイは東北へのご縁が広がることを願って、宮城県 南三陸町へ送り、現在はアジサイの代わりに宮城県県花のハギを植えているそうです。 一面のアジサイはもう見られませんが、今後はハギを楽しみにしたいです。 山門前から見える弧を描いて広がる由比ヶ浜、材木座海岸の一望は健在で、鎌倉でも屈指の絶景ポイントになっています。 コロナ禍でお守りやご朱印などセルフ対応でした。 前回はコロナなど知らない頃の暑い日の参拝だったため、暑さに気をつけての心づかいと塩味せんべいをくださったこと、懐かしく思いました。 平穏な日々に戻ることを祈るばかりです。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 鎌倉市手広にあるお寺です。 手広の交差点を腰越方面に7〜8分ほど歩いたところにあります。私はお散歩がてら家から歩いて行ったのですが、最寄り駅の大船や藤沢から歩くには少々遠いのでバスを利用した方が良いと思います。 入口の前は駐車スペースなのか少々広くなっていて数台であれば駐車することが出来そうでした。 山門の両脇にある石碑や看板に「鎖大師」や「鎖弘法大師」と書いてあったので少々不思議に思いました。看板によると本尊の鎖大師像は重要文化財に指定されているようです。 緑色の屋根の山門をくぐるとまっすぐな参道になっており、その両側に建物と石像がある造りとなっていました。 入って直ぐの右側に手の込んだ立派な屋根の鐘楼があり、感動しました。 更に参道を進んで行くと本堂が右側にあり、お線香が売っていたので購入してお参りをしました。 扁額に「鎖大師」と書いてあったので、この中にあるのかと思いましたが扉が閉まっていたので見ることが出来ず残念でした。 参道を挟んで本堂の向かい側に五輪塔童子という小さな石像がありました。5体の石像があり、それぞれがラッキーカラーと健康運や勝負運等のご利益を持っているようです。このような石像を見たことは無かったので、良い体験をすることが出来ました。 「鎖大師」というのが気になったので帰宅後に調べてみると、弘法大師木像の膝が鎖で繋がっていて動くようになっていることから「鎖大師」と呼ばれるようになったそうです。 弘法大師自身が作ったと伝えられているようです。 年に5回開帳されるとのことなので、機会があれば行ってみたいと思います。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 鎌倉市梶原にある神社です。湘南モノレール湘南深沢駅から歩いて10分くらいのところにあります。深沢小学校を目指していくと直ぐ横なので分かりやすいです。 入口から真っすぐに伸びる参道を進み、鳥居と2つくぐると拝殿があります。拝殿を通してその先に本殿へと続く階段が見えるのが少し変わった造りだと思いました。 横にある由緒が書いている石碑を読むと、御祭神は鎌倉権五郎景政で鎌倉幕府が出来る前に源頼義とともに奥州の合戦で活躍した人物のようです。1190年に出来たらしく、歴史のある神社のようです。 拝殿を過ぎ、更に階段を上って行くと本殿に着きます。建物自体は大きくないのですが、岩山を切り開いて建てられた境内の雰囲気は神聖さを感じました。 また、岩肌を掘って何かをお祀りしている石碑が幾つもあり、更に厳粛な雰囲気を感じさせました。 境内は全体的に手入れがされており、とても清々しい雰囲気です。本殿周りの苔の生え具合が良い雰囲気を出しているなとも感じました。 神社の周りに小学校の他に中学校も直ぐそばにあり、とてもいい環境だと思いました。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 龍口明神社は古墳時代の538年創建で、鎌倉市に現存する一番古い神社と言われています。五頭龍大神と玉依姫命を祀っています。五頭龍大神は国家安泰・心願成就・交通安全・縁結び、玉依姫命は縁結び・子授け・安産の神として信仰されています。 玉依姫命は神武天皇の母、海神族の祖先で、龍神として崇められたと伝えられています。五頭龍大神とは、鎌倉と江ノ島に伝わる五頭龍と弁財天の伝説に登場する一身五頭の龍神で、江の島の弁財天に悪業を戒められた龍であり、龍が改心し岩山と化した後、津村(腰越および隣接の現鎌倉市津一帯)の村人達が、龍の口にあたる岩上(龍口)に社を築いて、村の鎮守としたことが、龍口明神社の発祥と伝えられています。と言うことで、現在の西鎌倉では無く、当初は龍口寺西隣にありました。大正12年(1923年)、関東大震災により全壊し、その後、昭和8年(1933年)に改築しました。しかし、鎌倉時代に刑場として使用された時期もあったこの地の祟りを恐れた氏子の要望により、 昭和53年(1978年)に江の島を遠望し、龍の胴にあたる現在の地へと移転したそうです。 最寄り駅は湘南モノレール線西鎌倉駅で、歩いて5分と案内されていますが、坂道ということもあり、もう少しかかるかもしれません。閑静な住宅地の中にあり、境御神木のタブノキや五頭龍大神の銅像などがパワースポットとして人気になっています。 また、移転前の龍口(龍口寺)には、鎌倉市津1番地が飛び地として残っています。龍口明神社跡は中に入れないようになっていますが、通りから鳥居が見えます。 日本三大弁財天として名高い江島神社とは夫婦神社(江島神社が女、龍口明神社が男)とされ、江島神社と龍口明神社は併せてお参りされるがおすすめであると言われています。また、現存する一番古い神社という事ですので、移転前の龍口明神社跡にも立ち寄りたいですね。この辺りは歴史のある神社も多く、神社仏閣巡りに良いところです。併せてお参りに行ってみてください。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 片瀬の諏訪神社は今から1300年余り前(奈良時代)養老7年(723年)に信濃国(長野県)諏訪大社からの御分霊として上下両社に鎮座されたとのことです。片瀬の地は現在とは地形が異なり、以前は水面の覆われた大きな沼湖で、それが諏訪湖を取り巻く諏訪の地によく似ていたことからこの地が選ばれたとか。。。全国各地にある諏訪大社の御分霊を祀る諏訪神社の中でも最古のものとされているそうです。 令和5年(2023年)に創建1300年を迎え、令和5年(2023年)10月22日に「御鎮座1300年奉祝祭」が盛大に執り行われ、「御鎮座1300年記念の木札守・切り絵御朱印」が奉製されました。 下社は江ノ電 湘南海岸公園駅より徒歩5分、江ノ電バス 江の島行き方面 諏訪神社前が参道入口になります。参道砂利道の一の鳥居をすすみ、道をへだてて、2の鳥居へ、左側に手水舎があり、コロナ流行に伴い、柄杓はなく、手をかざすと水が出てくる方式になっています。1300年つづくこの神社も長い歴史の中でも色々変わったことも多いのでしょう。社務所は下社のみで右側に進んだところにあります。受付時間午前10時頃〜夕方5時までとのことで、拝殿もその時間ぐらいに閉じられている感じです。 七五三詣の時期はご祈祷と祝詞をあげてもらったりしているのに遭遇します。お参りを遠慮した方が良いのかなと思ったりしていましたが、そうゆう時は神様からの歓迎のサインと本で読んだこともあり、来年はお祝い事の日がお参りしたい時に重なってしまっても遠慮せずにお参りしようと思います。「みんなが幸せになるように!」と。 上下両社を備えているのは信濃諏訪本社と片瀬の諏訪神社のみとのこと。上社への行き方は下社入口に案内板があります。住宅地の道を進んで行くので、ちょっと不安になりますが、道なりに左へ進んでいくと上社入口の通りに出ます。近くの人は知っているので、不安があったらすぐに聞いてみてくださいね。上社は階段を上ったところにあり、片瀬の町が一望、江ノ島や天気の良い時は富士山が見えるところなので、是非上社もいっしょに参拝に行ってください。お賽銭箱は階段の下側にあり、社殿の門はいつもは開いていません。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 密蔵寺は江ノ電の江ノ島駅や湘南モノレールの湘南江の島駅近くの江ノ島駅入口交差点から北に向う道を10分程歩いていくと右側にあり、迷わず分かりやすい場所です。まわりは住宅地なので静かなところです。以前はお寺が経営していた「みふじ幼稚園」がお寺から数分のところにあり、近隣の子供たちが通っていました。そのようなこともあり、近隣の方たちには親しみあるお寺ですね。門前には愛情観音も安置されていて、その頃のことを思い出します。幼稚園の跡地には住宅が建ち並び跡形もなく、多くの子供たちが通ったところなので、寂しいですね。 真言宗大覚寺派寺院の密蔵寺は、寶盛山薬師院と号し、有辨(徳治元年1306年寂)が開山し、與(天正5年1577年寂)や良忍、全道による再建を経ています。何度かの火災にあったそうです。東国八十八ヵ所霊場87番、相模国準四国八十八ヶ所17番、相模国大師廿一霊場17番です。 本尊は創建時から薬師如来(医療と健康の守護仏)ですが、本堂に祀られている愛染明王(敬愛、間関係を良くする)の方が知られているようです。 境内にはカツラの木「愛染かつら」やイチョウの木があります。大イチョウの木の下に六地蔵が安置されています。秋にはイチョウの素敵な紅葉が見られます。一時期、この辺りの木々は塩害にあったりしましたが、昨年行ったときは綺麗に色づいていましたね。塩害を受けなかったのかもしれませんが無事で良かったです。本堂前には古来より熊野大社の御神木である梛(なぎ)の木と「四国八十八ヶ所御砂踏霊場」があります。お砂踏みとは、四国八十八箇所霊場のお砂を納めているので、東西南北の4度合掌してお祈りをすると、四国八十八箇所を巡拝したのとの同じご利益があるというもの。本堂は平成17年創建700年の記念事業で建立されたとのこと。境内には歴史を感じる古い石像などあります。 また湘南江ノ島安らぎ霊園 湘南江ノ島樹木葬プラチナヒルズ樹木葬のお墓が境内にあるので、案内の旗が通り沿いの出ていて目印になっていますね。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 常立寺(じょうりゅうじ)は日蓮宗のお寺です。当初、真言宗の回向院利生寺として創建され、その後、享禄5年(1532年)に日蓮宗へと改宗し、今の名の常立寺になったそうです。 1275年、元(蒙古)の使者杜世忠(とせいちゅう)ら5名がフビライの国書を携え、無条件降伏を迫って来日します。時の執権北条時宗が徹底抗戦を決意し、5名の処刑を命じ、龍の口の刑場で処刑されました。その5人の亡骸を葬った五輪塔がある事で知られているお寺です。山門をくぐった左手に高さ2メートルあまりの供養塔があります。こちらの内容は表通りからの入口の「伝元使塚」(藤沢市教育委員会)に記載されています。 そのため、平成17年(2005年)4月7日に朝青龍や白鵬らモンゴル出身の幕内・十両力士らが元使塚を参拝しています。モンゴルで青い布(青はモンゴルで英雄を意味する色)を五輪塔に巻き、元使を弔いました。その後も毎年、藤沢大相撲巡業の際にモンゴル出身力士による元使塚参拝が行われるようになり、五輪塔には常に青い布が巻かれるようになったようです。また、平成19年(2007年)3月1日には、モンゴル国大統領のナンバリーン・エンフバヤル夫妻も参拝しているそうです。その時に植えた梅の木が五輪塔のそばにあります。 今年は2月15日に「梅まつり」を開催して、境内にお茶席やこども縁日が出店したとか。見頃の時期は通りからもキレイな梅の花が覗け、ご自由に参拝くださいの案内があり、普段はひっそりとしている境内も多くの方が写真を撮ったりした、賑わっています。参拝した時にお茶席が設えてあり、どうやら「梅募金」という取り組みらしく、梅の維持費のために300円の募金をすると、お茶とお菓子を出していただけるようです。ライトアップも2月1日(土)から24日(月)の日没から午後9時まで行われ、日没後も梅を楽しむことができ、春の訪れを存分に味わえるように演出しています。梅の時期の他に、秋の紅葉の時期はイチョウがとてもキレイで同様に夜ライトアップを行っているようですよ。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 神奈川県鎌倉市長谷にある収玄寺は、江ノ電長谷駅から徒歩わずか1分の場所に位置する日蓮宗の寺院です。観光客で賑わう長谷寺や鎌倉大仏への道中にありながら、静かで落ち着いた雰囲気を保っています。境内は四季折々の花々が彩り、特に春の桜や夏のアジサイ、秋のシュウメイギクなどが訪れる人々の目を楽しませています 。 ? ? この寺院は、鎌倉時代の武士で日蓮の信徒であった四条金吾頼基の邸宅跡に建てられました。境内には「四条金吾邸址」と刻まれた大きな石碑があり、その文字は日露戦争で連合艦隊を率いた東郷平八郎によるものです 。また、境内にはカフェ「蕪珈琲」も併設されており、参拝後のひとときを過ごすのに最適です 。 ? ? 境内はは、綺麗に手入れされていて、赤や白、ピンクに青、色とりどりのアジサイが美しく、静かに歴史を感じられる場所としても評価されています。 ? ? 収玄寺は、華やかな観光地の喧騒から少し離れ、鎌倉の歴史と自然を静かに感じられる場所です。長谷エリアを訪れる際には、ぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。
ホームメイト・リサーチに
口コミ/写真/動画を投稿しよう!
「口コミ/写真/動画」を投稿するには、ホームメイト・リサーチの「投稿ユーザー」に登録・ログインしてください。
Googleアカウントで簡単に最も安全な方法で登録・ログインができます。

ゲストさん
- ゲストさんの投稿数
-
今月の投稿数 ―施設
- 累計投稿数
-
詳細情報
―件
口コミ
―件
写真
―枚
動画
―本