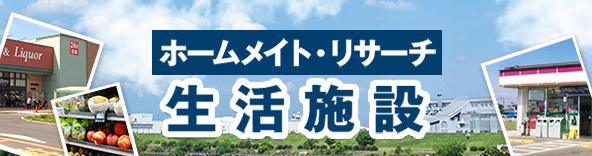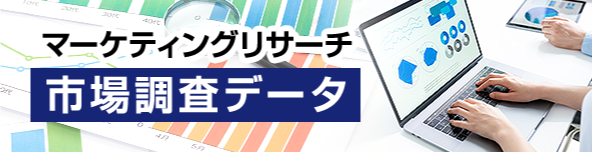徳島県 の観光スポット・旅行(1~30施設/291施設)
徳島県の観光スポット・旅行・レジャーを一覧でご紹介します。「旅探たびたん」では、徳島県にある観光施設の所在地の他に、皆様から投稿頂いた情報を一覧にて表示。施設名をクリックすると観光スポット・旅行・レジャーの詳細情報はもちろん、目当ての観光施設周辺の情報を確認することができます。徳島県で観光・旅行したい方におすすめです。観光スポット・旅行・レジャー一覧は、①アクセス数、②動画、③写真、④口コミの多い順に掲載しています。
※施設までの距離は、直線距離から算出し表示しております。直線距離の確認・目安としてご活用ください。
実際の正確な道路距離・所要時間・経路については「施設までの徒歩経路」ボタンをクリックし、「Googleマップ」にてご確認をお願いします。

四国地方
- 徳島県の観光スポット
- 291施設
- ランキング順
-
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 徳島県鳴門市にある「大塚美術館」に行ってきました。ここは日本最大級の陶板美術館として知られていて、展示されている作品はすべて陶板で再現されたもの。 正直、陶板と聞いて「本物じゃないんだ」と思っていたのですが、実際に足を運んでみるとその考えが一変しました。 まず驚かされたのが、古代遺跡や教会の壁画などが、空間ごと再現されている点です。たとえばシスティーナ礼拝堂の天井画や、ギリシャの壁画などが、建物のスケールそのままに展示されていて、その場に立つだけでまるで海外に来たような感覚になります。天井を見上げたときのスケール感は、まさに圧倒的。写真や映像では味わえない迫力がありました。 また、「テレビや雑誌等で見たことがある」有名な国際的名画がずらりと並んでいるのも嬉しいポイント。モナ・リザや最後の晩餐、ゴッホやモネの代表作など、教科書や美術番組で一度は見たことがある作品が間近で見られます。しかも、それぞれの絵には丁寧な解説がついていて、美術にあまり詳しくない僕でも「なるほど、こういう意味だったのか」と理解しながら楽しむことができました。 館内は広く、地下3階から地上2階までとかなりのボリューム。展示だけでなく、休憩スペースやカフェも充実しているので、時間をかけてじっくり鑑賞するのがおすすめです。特に鳴門の自然光を活かした展示エリアは、絵画と風景が一体になっていて、とても印象的でした。我が家の場合は、脚の悪い両親も一緒だったので、1日かけてゆっくり巡りましたが、元々絵画が好きな両親は本当に喜んでくれたので連れてってあげれて良かったです。 「大塚美術館」は、美術に詳しくない人でも、旅の中で気軽に芸術に触れられる貴重な場所です。徳島観光のついでに立ち寄る価値は十分ありますし、「鳴門=渦潮」だけじゃない、新しい魅力を発見できるスポットだと感じました。鳴門に行く機会があれば、ぜひ訪れてほしい場所のひとつです。
-
鳴門海峡(大鳴門橋架橋記念館)
所在地: 〒772-0053 徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦字福池65
- アクセス:
「「鳴門公園」バス停留所」から「鳴門海峡(大鳴門橋架…」まで 徒歩1分
神戸淡路鳴門自動車道「鳴門北IC」から「鳴門海峡(大鳴門橋架…」まで 2km
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 鳴門海峡は徳島県の名所です。先日車で行ってきました。最高な天候でクルーズ船から世界最大級の渦潮を見る事ができました。 大鳴門橋から見える渦潮は大迫力です!非常にオススメな観光スポットです!
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 徳島県三好市にある祖谷のかずら橋は、日本三奇橋の一つに数えられる伝統的な吊り橋です。深い渓谷に架かるこの橋は、スリル満点の体験ができる観光スポットとして知られると同時に、平家伝説が息づく歴史的な場所でもあります。そんな祖谷のかずら橋の魅力を詳しく紹介します。祖谷のかずら橋は、鉄やコンクリートを使わず、植物のツル(シラクチカズラ)を編み込んで作られているのが特徴です。長さ約45メートル、幅約2メートル、高さ約14メートルの橋は、見た目もワイルドで、自然と調和した美しい造りになっています。かずら(シラクチカズラ)は3年ごとに架け替えられるため、常に新しい状態が保たれています。植物の橋を渡るという珍しい体験は、他の吊り橋ではなかなか味わえません。かずら橋の床板は木の板でできていますが、その間隔が約15〜30cmほど空いており、足元から真下の川が見えるため、歩くたびにスリルを感じます。特に高所が苦手な人にはドキドキする体験となるでしょう。かずら橋の起源は、平家の落人伝説にあります。平安時代、源氏に敗れた平家の一族が四国の山奥に逃れ、その際に敵の追跡を防ぐために、いつでも切り落とせるかずらの橋を架けたと言われています。そのため、この橋には歴史的なロマンが詰まっています。祖谷のかずら橋が架かる祖谷渓は、四国でも有数の秘境として知られています。深い渓谷の中を流れる祖谷川の透明な水、四季折々の美しい風景は、訪れる人を魅了します。かずら橋を訪れたら、ぜひ立ち寄りたいのが祖谷温泉。源泉かけ流しの温泉で、露天風呂からは祖谷渓の絶景を一望できます。秘境ならではの開放感を楽しめる温泉です。また、祖谷渓には「小便小僧像」というユニークな観光スポットがあります。渓谷の断崖絶壁に立つこの像は、かつて地元の子供たちが度胸試しをした場所に設置されたもの。スリル満点の絶景スポットとして人気があります。祖谷のかずら橋は、スリルと歴史、そして自然の美しさを兼ね備えた唯一無二のスポットです。秘境ならではの大自然に囲まれたこの橋を渡れば、平家伝説に思いを馳せながら、スリリングな体験ができます。さらに、周辺には温泉や絶景ポイントもあり、訪れる価値のある観光地です。ぜひ一度、祖谷のかずら橋で非日常の体験を楽しんでみてはいかがでしょうか?
-
阿波おどり
所在地: 〒770-0847 徳島県徳島市幸町2丁目(会場)
- アクセス:
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 阿波踊りは、阿波国発祥とする盆踊りで日本の伝統的な祭りであります。徳島県の阿波地方で毎年8月に行われる踊りの競演です。阿波踊りは、その踊りのスタイルや音楽、踊り手たちの動きの美しさで広く知られています。全国各地から観光客が訪れていて熱気に包まれていました。 阿波踊りは、江戸時代の1600年代にさかのぼる歴史を持っています。当初は祭りの一環として行われていましたが、次第に人々の間で人気を博し、祭り自体が阿波踊りのための大規模なイベントへと発展していきました。 阿波踊りの最も特徴的な要素の一つは、踊り手たちが鳴り物や笛、太鼓などを演奏しながら、踊りながら進むことです。その音楽は、軽快でリズミカルなものであり、踊り手たちのリズムに合わせながら進んでいきます。また、踊り手たちは着物や浴衣を着用し、独自の踊りのスタイルを披露します。 阿波踊りの踊り手たちは、団体ごとに異なる踊り方や衣装、演奏スタイルを持っており、競演の際には競い合います。踊り手たちは熱心に練習を重ね、年間を通じて踊りの技術を磨いてきます。 阿波踊りは、地元の人々だけでなく、全国各地や海外からも多くの人々を魅了しています。祭りの期間中は、参加者や観客が集まり、賑やかな雰囲気が広がります。特に、仲間と一緒に踊ることで結束を深めるという意味もあり、地域コミュニティの絆を強める一助にもなっています。 阿波踊りは、日本の文化や伝統を守り続ける重要な要素であり、その美しく迫力ある踊りは、多くの人々の心を魅了しています。阿波踊りの祭りを訪れると、歴史や文化に触れ、日本の祭りの魅力を存分に味わうことができます。 地元の方々だけではなく、根強い阿波踊りに魅せられた方々が多くいらっしゃる事に感動しました。阿波踊りは、その美しい踊りと伝統的な雰囲気で、多くの人々に愛されています。是非、一度その魅力に触れてみてください。一度行ってみたらまた行きたいと思うのですが、自分の住んでいる所からは遠いのが残念です。 でも是非もう一度行ってみたいと思います。
-
井戸寺(第17番札所)
所在地: 〒779-3118 徳島県徳島市国府町井戸80-1
- アクセス:
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 徳島県にある。四国八十八ヶ所。第十七番札所の井戸寺。「いどでら」ではなく「いどじ」と言います。元々は妙正寺でしたが、おだいさまが井戸を掘って近所の人が井戸のあるお寺。井戸のある寺というようになって井戸寺になったそうです。地域の方に伝わるのが井戸の中を除き顔が映ったら無病息災。顔が映らなかったら3年以内に悪いことがおきると言われています。おもかげの井戸は覗きこんだ時に危なくないように網がしてあります。想像よりも水は浅いところにあります。映らなかったらというドキドキで覗きますがちゃんと写ってよかったです。綺麗な水がなくおだいさまが井戸を掘った事で街が潤ったとの事です。井戸寺は瀬戸内寂聴さんが眠っている寺として有名です。元々縁があるわけではなく納骨堂のパンフレットを見て気に入って決められたそうです。 地下に納骨されているとの事です。薄いピンクの色のガラスのオブジェがとても綺麗で安らかに眠っているように感じました。全国的にも珍しい七仏薬師如来という聖徳太子が掘ったと言われる御本蔵だそうです。西暦673年に建てられたこの井戸寺は1350年になるそうです。建物も立派でお大師堂が1番古く江戸の後期ぐらいの建物だそうです。作りがしっかりしていてとてもかっこいい印象です。50年ぐらい前に火災になってしまったそうで本堂の中の修復が終わった頃に火事になってしまったそうです。聖徳太子が作ったと言われている薬師如来は家事に近所の方達によって救出されたそうです。たくさんの方達に支えられて、古いという事ではなくその歴史や風景に時代を感じます。見どころは面影の井戸。日限大使。仁王門です。是非参拝されてみてください。お遍路にきてみてください。ここ井戸寺は徳島県徳島市国府町井戸北屋敷80-1にあります。遠方から行かれる方は藍住インターチェンジで降りてください。駐車場は30台ほどです。長期連休には混雑する可能性があります。
-
阿波おどりミュージアム
所在地: 〒770-0904 徳島県徳島市新町橋2丁目20
- アクセス:
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 徳島市新町橋二丁目にある阿波おどりミュージアムです。開館時間は朝9:00から夜20:00までですが時期によっては時間が変わる場合があるので事前確認したほうがいいです。休館日は2月、6月、9月、12月の第2水曜日と年末年始になります。この施設は徳島の阿波踊り関連の展示、実演を行っている施設になります。伝統技能の阿波踊りを年間を通じて楽しむ事をコンセプトとしています。外観は高張り提灯をモチーフに5階建てで建設されています。1階は観光コーナー、2階は阿波踊りホール、3階は阿波踊りミュージアム、4階は活動室、5階眉山ロープーウェイ山麓駅となります。駐車場は建物や近くにあります。阿波踊りホールは席数250席ある、踊りを鑑賞できるホールになります。午前、午後の2部制になり、午前は専属の躍り連、午後は各有名連が日替わりで出演します。一度HPの確認お願いします。入場料は大人¥1000,小、中学生¥500になり、体験をすることが出来ます。
-
雲辺寺(第66番札所)
所在地: 〒778-5251 徳島県三好市池田町白地ノロウチ763-2
- アクセス:
高松自動車道「大野原IC」から「雲辺寺(第66番札所…」まで 8.5km
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 雲辺寺(第66番札所)は香川県善通寺市にあるお寺で四国八十八ヶ所の1つになります。山の上にお寺があるため歩いてくのが大変で今回はロープウェイを使ってお参りに来ました。私が行った時期は紫陽花が綺麗でした。 境内は山の中の為か結構アップダウンがあるので注意が必要です。 でもとても自然を感じることの出来るいいお寺でした。
-
常楽寺(第14番札所)
所在地: 〒779-3128 徳島県徳島市国府町延命606
- アクセス:
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 第十四番札所 盛寿山 常楽寺 延命院へ行ってきました。 第十三番から約1kmほど歩くと、道は鮎川に架かる橋を渡ります。そこからは、マイカーなら鮎喰川の流れに沿って県道207号線を使います。歩きの遍路なら橋を渡って左折、旧遍路道を行 くことになります。そこから少し歩けば、 小高い丘の上に建つ常楽寺の伽藍が見えてきます。 車窓から眺める流域の風景もいいですけど、川沿いから離れて集落や田園の中を歩く旧道もなかなかに味があるんじゃないでしょうか。このあたりは車も少なく、のどかな風情にひたりながら巡礼の旅を楽しむことができるでしょう。春や秋ならば、吹き抜ける風も心地よいと思います。遠くの山々には、木々の緑も美しく映えるのが見えるでしょう。 参道の登りはややきついですが、周囲の奇岩が目を楽しませてくれます。手すりも用意されているのでゆっくり歩けば楽しいです。 歴史と由来についてですが、弘仁6年 (815)、弘法大師がこの地で7日間の修行をしたときに創建した寺とされています。このとき、大師は弥勒菩薩のご来迎を拝し、その姿を2尺6寸 (約80cm) の像に刻んで堂宇を建立したといいます。美定 ※年間 (1573~92)の兵火でこの寺の堂宇も焼失してしまったのですが、 その後、江戸時代になって阿波藩主・蜂須賀光隆により再興されています。ちなみに、 弥勒菩薩を本尊とするのは四国八十八ヵ寺のなかでもここが唯一です。 しかも、ここの本尊は、京都と滋賀県にある三井寺の本尊とともに「日本三体」のひとつに数えられる傑作仏像として、高く評価されているのです。 利益とエピソードについて。本堂や大師堂をおおうようにして枝を広げる大木。これは「あららぎの霊木」と呼ばれる弘法大師ゆかりの老樹で、あらゆる病に霊験を発揮するといわれています。 みどころですが、平野にぴょこんと飛びでた丘の上にある境内は、周辺の眺望も素晴らしく、四季折々の変化を楽しませてくれるだろのでおすすめです。また、境内には 「流水岩の庭園」と呼ばれる名所もあります。露出した天然の岩肌が庭園の樹木と調和して、印象深い風情を醸していますね。 現在、水は流れていませんが、その光景はまさに水の芸術ですよ。四国を代表する名作庭園との評判も高いらしいので、一見の価値ありです。
-
眉山ロープウェイ
所在地: 〒770-0904 徳島県徳島市新町橋2丁目20
- アクセス:
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 徳島市新町橋2丁目20にある徳島市のシンボル眉山にあるロープウェイです。標高約290mの山頂からは天気が良ければ絶景が望めます。四国八十八景(眉山ロープウェイから望む水都徳島の風景)にも選出されています。歩いて上るのもいいですがロープーウェイを使えば約6分ほどで山頂に着きます。営業時間は時期により異なるので一度HPなどを確認してください。出発口には阿波踊り会館の5階にあるのでそちらを訪ねるついでにロープーウェイで山頂に行くのもありだと思います。山頂では四季折々の景色が楽しめるので何回行っても楽しめます。徳島駅から約10分ほど歩くと着きます。利用料金は大人片道¥620-、往復¥1030-、子供片道片道¥300-、往復¥510-になります。乗る際は往復券を買う方がいいと思います。約15分に一回出発しているので混雑時にもそれほど待つことなく利用できます。阿波踊りと眉山を堪能しないと徳島を楽しむ事はできませんよ。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 第十番札所 得度山 切幡寺灌頂院へ行ってきました。 寺への道ですが、第九番の法輪寺からは幹線道路を進んでいきます。約3kmほど行ったあたりで右折して、徳島自動車道の下をくぐり抜けて、切幡寺へ通じる山道へ入る感じになります。ここからが、今回のルートの最難所!バスもこのあたりまでしかないので、マイカー利用者以外は自分の足で歩くしかないですよ! 徒歩で行くならば舗装道路よりも、それに平行してある旧道のほうがおすすめです。 旧道は昔からの遍路道でもありますし、沿道の風情も素敵です。車にでくわすこともないので、のんびりと周囲の自然を愛でながら歩くことができます。境内までの所要時間は、ゆっくり歩いて約1時間くらい。道沿いに杉の古木が繁る森が見えてくると、もう札所は近いです。 歴史と由来についてですが、弘法大師が四国巡錫の旅の道中で、この地に立ち寄ったとき、着物が破れて困ってしまいまして、近在の民家に縫いの布を求めると、このとき、家の中で機を織っていた娘が、織りかけていた布を惜しげもなく切り裂いて与えてくれたのだとか。 この娘の行為に感動した大師は、お礼に千手観音を刻み、娘を得度させて灌頂を授けたところ、彼女は七色の光を放って千手観音に変身したという逸話があります。その観音像が境内に立っているのです。その後、大師は嵯峨天皇に奏請して、この地に寺を建立しました。寺名、院号、山号はすべて、 大師が遭遇した不思議な出来事にまつわるものです。 みどころ等としては、標高155mの境内は自然環境も素晴らしく、四季折々に美しい草花が眺められる点です。なかでも春は梅や桜の名所として名高いですし、また、山腹の地にあったために戦国時代の兵火にもあわず、境内には古い文化財が多数所蔵されています。なかでも、本堂に安置された弘法大師作の本尊、千手観音像は歴史的価値も大きいとされ、本堂奥の院には、創建時の伝説にまつわる娘が即身成仏したといわれる2体の秘仏も現存しています。 また、山中にある大塔は徳川二代将軍・秀忠が堺の住吉神社に寄進したものですが、明治時代の神仏分離令によってこちらへ移築、現在は国の重要文化財に指定され、日本三大塔のひとつにも数えられるのだとか。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 第十一番札所金剛山一乗院藤井寺へ行ってきました。 徳島自動車道の高架を抜けます。四国電力前で、道は県道12号線にあたります。それを左折してしばらく行くと、大野病院や徳島銀行などがある国道318号線が交わる十字路にでます。ここで右に曲がり、国道を歩くとやがて吉野川の雄大な流れが目の前に現れます。ここまで来れば、十一番目札所藤井寺はもう間近です!川辺でしばしの休憩、四国随一の大河の眺めを楽しむのもいいかも。 吉野川を渡るとすぐに、国道192号線につきあたるT字路です。これを左へ、鴨島駅の方向に歩くと参道が右手に見えてきます。十番札所からの距離は約11kmです。山門を入ると見事な藤棚がさっそくお出迎え。5月上旬には紫や白の華麗な花をつける、天然の休憩所です。春には桜、秋には紅葉が美しいです。 歴史と由来については、四国を巡錫中の弘法大師がこの地を訪れたとき、村では疫病が流行していたそうです。このとき、大師は薬師如来を刻んで本尊とし、堂宇を建立して祈願しました。すると、間もなく村人の疫病は平癒したといいます。これが藤井寺の発祥にまつわる伝説で、寺の創建は弘仁年間(810~24)といわれています。 大師ゆかりの寺として、創建当時は七堂伽藍が建ちならぶ大寺院でした。本尊の薬師如来も「藤井寺のお薬師さん」として、人々に厚く信仰されていました。しかし戦国時代、長宗我部氏が阿波の支配を狙って兵乱を興し、このときの戦火で寺は荒廃。また、天保3年(1832年)には失火によってほとんどの堂宇を焼失しています。現在ある本堂や大師堂は、その後に再建されたものですね。 ご利益とエピソードについてですが、弘法大師作のご本尊薬師如来像は、四国に数ある仏像のなかでも最古のもので、重文にも指定されています。昔から厄除けの霊験があらたかなことでも知られ、病気の平癒などの参拝に訪れる人はたくさんいます。 弘法大師は、ここの境内から近い山上の八畳岩に護摩壇をつくり、17日間におよぶ悪疫退散の秘法を行ったといいます。かつての堂宇はすべて灰となったのですが、寺の発祥となった名所の岩は、いまも当時の姿で残っています。時間に余裕があれば、ぜひ見ておきたい大師の霊跡ですね。
-
国分寺(第15番札所)
所在地: 〒779-3126 徳島県徳島市国府町矢野718-1
- アクセス:
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 今回は、第十五番札所 国分寺 金色院へ行ってきました。 公共交通機関で行く場合は、JR徳島駅より矢野行きバス終点下車すぐ、車なら14番から約600m。道なりに進むと駐車場が仁王門前、 右手にあります。 第十四番札所からの距離は約600mです。本堂の重厚な屋根に、大寺院として知られまた往時の面影がほの見えます。 寺への道 常楽寺からはほぼ一本道となっていますね。鮎喰川の流れを汲んで広がる田園風景の中を歩いてゆくと、緑の絨毯の向こうに大きな伽藍が甍を並べて浮かんでいます。山門をくぐるとまず目に入るのが七重塔の礎石であったという大結晶片岩です。 近年、大師堂は焼けましたが、重層入母屋造りの本堂は変わらずに威容を誇っています。 歴史と由来についてですが、天平14年 (742) に国家の安泰を願って聖武天皇が全国に建てた国分寺のひとつです。建設を指揮したのは行基と言われています。その後、弘法大師も訪れ、第十五番目の札所に定めました。山門のわきには 「聖武天皇勅願所」 と彫られた石がいまも残っています。当時は四国随一の大寺院だったのですが兵火で焼失。江戸時代に再建されましたが、創建時の規模とは比べようもありません。 しかし、寛保年間 (1741~44) に建てられた本堂は当時を彷彿とさせ、壮大な寺院だったころの面影が残っています。 利益とエピソードについてですが、本堂の右手には、鳥沙摩明王を祀る堂があります。これは、大日如来の命を受けて悪を善へと導く仏様だといわれています。大師が唐から請来したもので、 不浄除けのご利益も絶大なのだとか。納経所には 「鳥瑟沙摩明王の札」も置いてあります。これをトイレに貼れば、子どものおねしょもピタリと治るとか。 みどころは、七重塔の礎石だけではなく、最近では発掘調査も進み、伽藍の回廊跡や寺域を示す溝の跡なども発見されています。 天平時代の大寺院を想像しながら、 境内を歩くのもよいのではないでしょうか。
-
ホームメイト・リサーチに
口コミ/写真/動画を投稿しよう!
「口コミ/写真/動画」を投稿するには、ホームメイト・リサーチの「投稿ユーザー」に登録・ログインしてください。
Googleアカウントで簡単に最も安全な方法で登録・ログインができます。

ゲストさん
- ゲストさんの投稿数
-
今月の投稿数 ―施設
- 累計投稿数
-
詳細情報
―件
口コミ
―件
写真
―枚
動画
―本